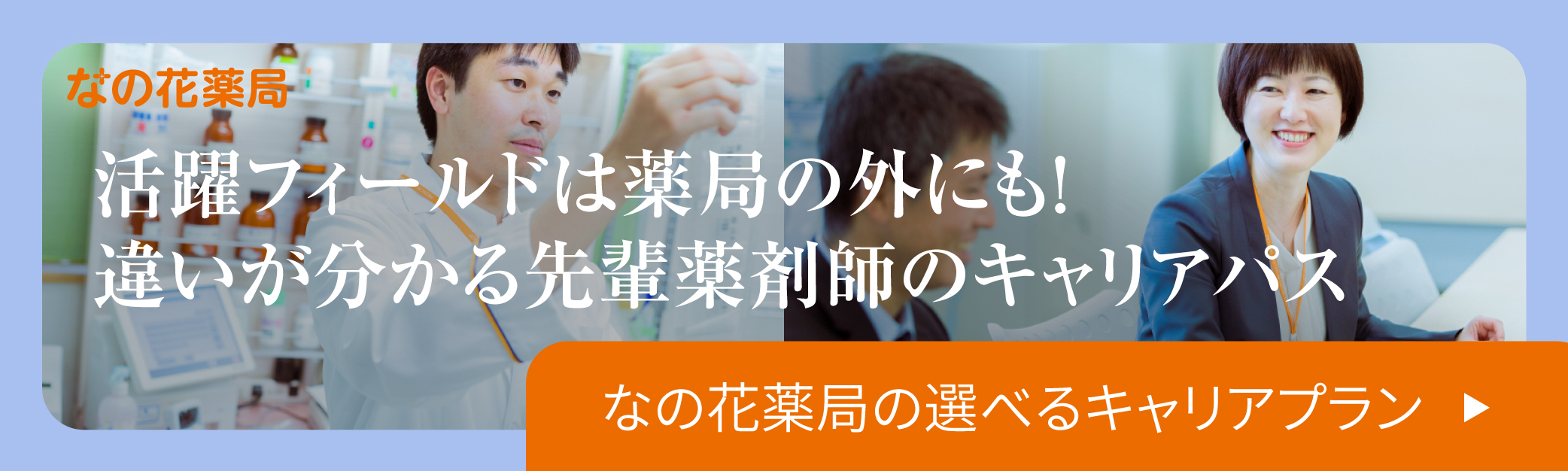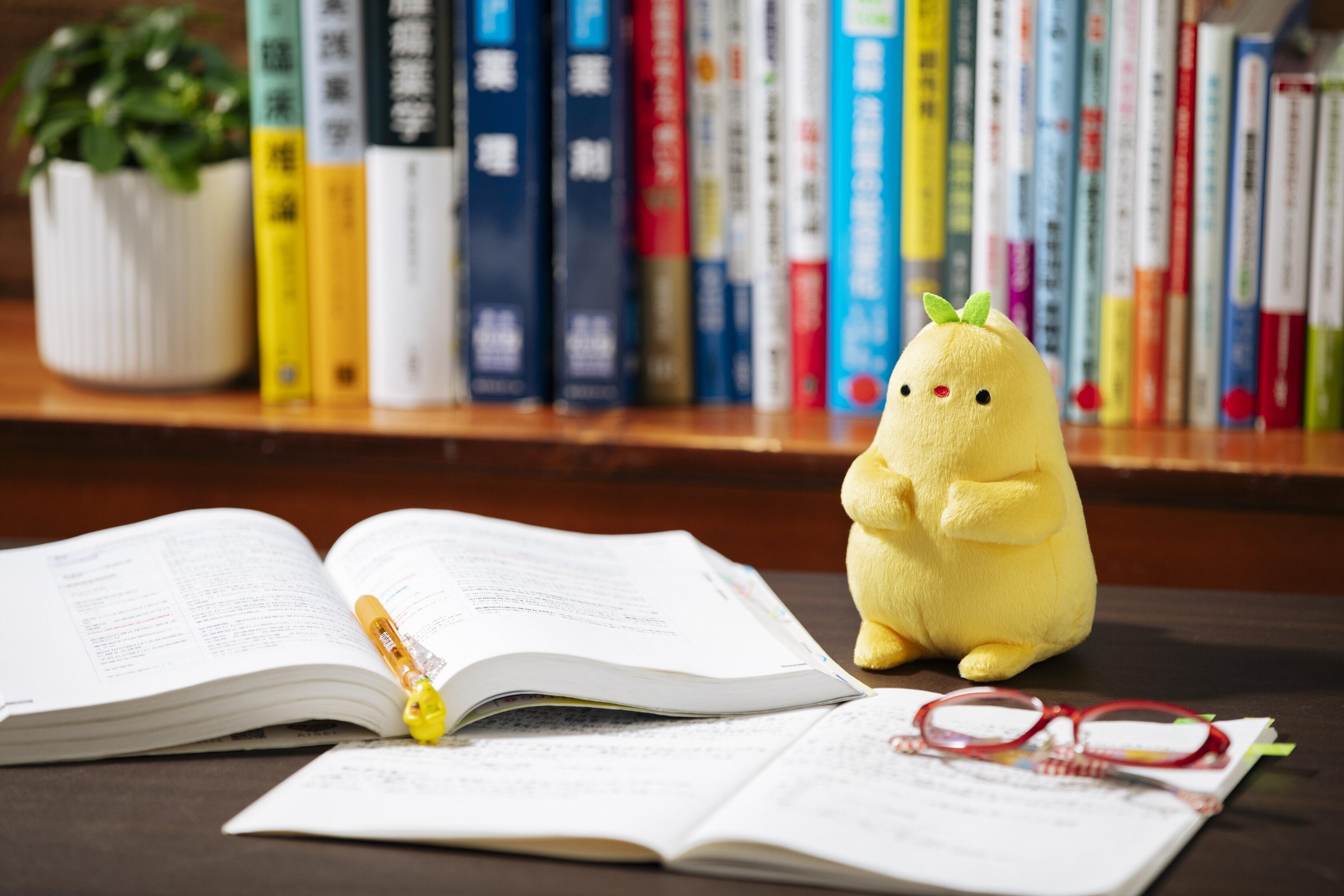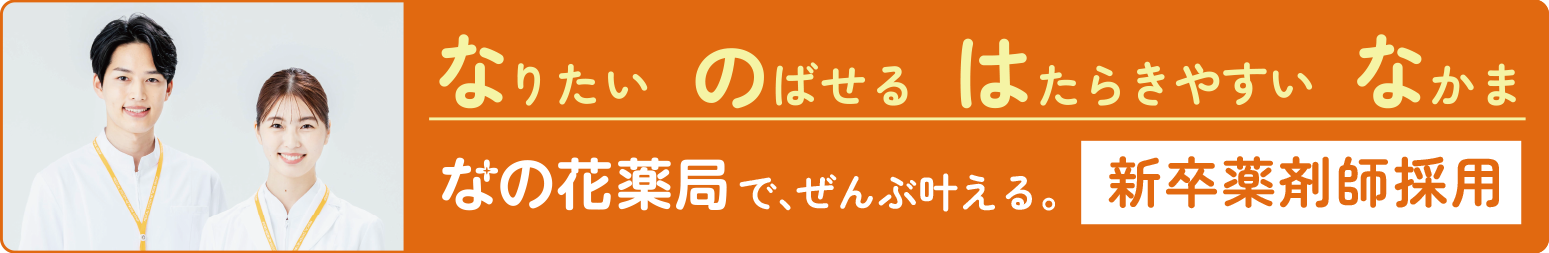2025.09.28
薬剤師の知識
薬剤師の離職率はどのくらい?長く働ける職場を選ぶポイントも
目次
こんにちは!なの花薬局の金原です。
薬剤師として長く働き続けるためには、職場選びが重要です。
長く働き続けることができる職場を見つけるための大切な指針となるのが、その職場の離職率です。
個々の職場の離職率が公表されていない場合でも、職種や店舗規模別、職場別で離職率がわかれば、職場選びの参考になります。
そこで今回は薬剤師の離職率について解説しながら、薬剤師として長く働き続けるための職場選びのポイントをご紹介していきます。

薬剤師の離職率はどのくらい?
離職率は、その職種や職場が「働きやすいかどうか」見極める目安となる情報です。
薬剤師全体の離職率と職種・規模別、職場別の離職率について見ていきましょう。
薬剤師全体の離職率は?
厚生労働省が公表している産業別の離職率(令和5年度)を見ると、薬剤師を含む「医療、福祉」業界における離職率は、14.6%となっています(参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」)。
同じく厚生労働省のデータによると、令和5年度の常用労働者全体の離職率は15.4%(参考:厚生労働省「令和5年雇用動向調査結果の概況」)です。
つまり、薬剤師を含む「医療、福祉」業界における離職率は、平均よりもやや低い数値であるといえます。
職業を薬剤師に絞った場合の離職率については公的なデータがないものの、一般的には10%程度といわれています。
職場別で見る薬剤師の離職率の傾向
職場によって、薬剤師の離職率は異なります。
具体的な数値は明らかになっていませんが、薬剤師の主な職場となる「薬局」「ドラッグストア」「病院」の3つについて、それぞれの離職率の傾向についてもお話しします。
薬局
薬局は勤務時間が決まっていて夜勤もないことがほとんどのため、安定した働き方が叶う職場です。
そのため、離職率はさほど高くはありません。
とはいえ、薬局でも離職する人は一定数います。
その理由は、日々の業務が人によってはルーティンワークに感じやすいという点にあるようです。
資格の取得などに挑戦して年収アップを目指したり、活躍の幅を広げたりと、目標を持って働くことも大切でしょう。
ちなみに、全国に482店舗(2025年8月31日現在)を展開する「なの花薬局」の薬剤師の離職率は7.64%(2023年〜2025年 薬剤師職)です。
待遇や休暇制度の充実、そして何よりも「全国で愛される『地域薬局』へ」という考えに共感した仲間が集まっているためだと考えています。
ドラッグストア
ドラッグストアで働く薬剤師の離職率も比較的低いと言われています。
柔軟な働き方が叶うドラッグストアでは、ライフスタイルに合わせた働き方が叶いやすいためです。
しかし、ドラッグストアの働きやすさは、会社や店舗によって大きく異なります。
中には人手不足から残業が多くなり、離職率が極端に高いドラッグストアも存在するでしょう。
離職率は5%〜10%程度と公表しているドラッグストアが多いです。
また、レジ打ちなどの関連業務も担当しなくてはならないため、薬局と比べ仕事量が多い可能性もあります。
病院
病院勤務の薬剤師の離職率は、薬局やドラッグストアと比べて高い傾向にあります。
その理由は、やはり病院勤務ならではの激務にあると考えられます。
病院薬剤師は業務量が多く、時間外の講習があったり、夜勤もこなさなければならない職場もあるため、負担が大きくなりやすいという点があるのかもしれません。
そのほか、CRO業界(医薬品開発受託機関)の離職率は10%程度、MRの離職率は企業によって大きく異なり5〜25%程度という情報もあります。
薬剤師の就職先別の仕事内容については、下記コラムもあわせてご覧ください。
薬剤師の就職先の選択肢は?仕事内容や就職状況、選び方を解説!
離職率が高い薬剤師の職場の特徴を知ろう

離職率が高い薬剤師の職場の特徴もご紹介します。
就職活動においては、検討する職場がこれらの特徴に当てはまらないかどうか、可能な限り事前にチェックできると良いですね!
① 給料の低さ
給料の低さは、働く人の不満につながりやすいです。
仕事内容や仕事量に対して給料が極端に低い職場では、当然離職率は高くなります。
また、賞与や手当の有無も確認しておく必要はあるでしょう。
②勤務時間の長さ
勤務時間が長かったり、不規則だったりする職場も、離職率は高い傾向にあります。
休日が少なく設定されている職場も同様です。
③人間関係が良好でない
これはどの業種でも同様ですが、離職率は人間関係にも左右されます。
入職前にその職場の人間関係を見極めるのは難しいですが、離職率や口コミなどが公開されていれば、そちらを参考にするのも良いでしょう。
④ステップアップが見込めない
職場によっては、キャリアアップや年収アップが見込めないことがあります。
そのような職場では「知識を増やしてキャリアアップを図りたい」「年収アップを目指したい」と考える薬剤師が自身のビジョンが叶う職場へと転職してしまうため、離職率が高くなることがあります。
面接の際などに、そういったステップアップが可能か確認しておくのがおすすめです。
⑤妊娠・出産後の働き方が整備されていない
特に女性の離職は、妊娠・出産や育児などのライフイベントが大きな要因のひとつです。
家庭の事情でフルタイム勤務が難しくなり、退職や勤務形態の変更を選ぶケースがあります。
産休・育休や時短勤務などの制度は整いつつありますが、職場のサポート不足や両立の難しさから離職を選ぶ人は少なくありません。
そのため、育児サポートなどの福利厚生が充実した企業を選ぶことも重要です。
薬剤師が長く働き続ける職場を選ぶためのポイント
最後に、薬剤師として長く働き続けることができる職場を選ぶためのポイントを、4つご紹介します。
ポイント1.離職率・定着率を確認
職場選びにあたっては、離職率や定着率が重要なポイントになります。
離職率・定着率については公表していない企業が多いものの、業界動向を公表するランキングサイトで調べられることもあるので一度チェックしてみましょう。
ポイント2.実際に職場を見学
気になる就職先があれば、ぜひ職場見学をしてみましょう。
仕事内容は同じでも、雰囲気は職場によって異なります。
実際に足を運んでみて、職場の雰囲気を感じたり、働く薬剤師の対応などを見たりすることが、入社後のミスマッチを防ぐことにもつながります。
なの花薬局でも、インターンシップにて店舗見学を実施しています。
薬局の雰囲気を感じられることはもちろん、「地域薬局」としての取り組みを学んだり、職員間の連携などを知ることができますので、興味のある方はぜひ一度参加してみてくださいね。
ポイント3.求める条件とやりがいを重視
長く働き続ける職場を選ぶなら、まずは職場に対する自身のニーズと、自身がやりがいを感じるのはどのような場面か考えておくと良いでしょう。
「どうステップアップしていきたいか」「どんな仕事・職場が理想か」という点で具体的にしておくと、応募する職場がやりがいを感じられる職場かどうか見極めやすくなります。
薬剤師のやりがいについては「薬剤師のやりがいは?やりがいを感じられない時の対処法も知っておこう」で詳しくご紹介しています。
また、なの花薬局では、ご要望に合わせてさまざまなキャリアパスをご用意しています。
下記ページで詳しくご紹介していますので、あわせて参考にしてみてくださいね。
薬剤師の選べるキャリアアップ
ポイント4.育児サポートの充実性を確認
薬剤師として長く働き続けるためには、働きやすい環境が整っているかを見極めることが大切です。
厚生労働省「令和5年度雇用均等基本調査」によると、育児休業終了後の復職者は、女性が93.2%。
産休や育休を取得した後にどれだけ復帰しやすいか、そして、安心してキャリアを築けるかどうかは、時短勤務や保育支援といった育児サポートをはじめ、福利厚生がどれだけ充実しているかが重要なポイントです。
「なの花薬局」では、産休・育休を取った後の復帰率が95%(2022年10月~2025年9月)と、多くの社員が安心して仕事に戻っています。
出産後は原則1年間の育児休業が取得でき、休業中も会社から最新情報が届くので、ブランクを感じにくい環境です。
復職後もお子さんが小学校1年生を終えるまで、1日最大2時間の時短勤務が可能。
さらに、スキルアップや生活サポート、子育て支援、文化・スポーツ活動の支援まで、福利厚生が幅広く整っています。
また、なの花薬局では、不安なことや悩みがあった場合、上司との定期的な面談のほか、いつでも相談できるホットラインも用意されており、安心して働ける体制が整っています。
自分がやりたい働き方を叶えるためには、就活時にしっかりと準備することが大切です。
下記コラムでは、就活を始める前にやっておきたいことなどをご紹介していますので、あわせてご覧ください。
薬学部が就活前にやることは?スケジュールや就活のコツなどを解説
薬剤師の離職率は低め!ただし職場による違いに注意を
薬剤師の離職率は全体で約10%といわれ、医療・福祉業界全体の14.6%より低い傾向にあります。
ただし、職場によって差があり、薬局やドラッグストアは比較的安定している一方、病院は業務量や夜勤の多さから離職率が高い傾向にあるといわれています。
離職を招く要因には、給与や勤務時間、人間関係、キャリアアップの難しさ、妊娠・出産・介護などの生活スタイルの変化などが挙げられます。
長く働くには、離職率や定着率の確認、育児サポートや福利厚生の充実度を見極めることが大切です。
自身の理想とも照らし合わせ、総合的に見て自分にマッチしそうな職場を選びましょう。
実際に職場を見学してみることも、入社後のミスマッチを防ぐためには大切です。
なの花薬局では、薬剤師を目指すみなさんへ就活サポートコラムを発信中です!
就活で悩んだときは、ぜひこちらのコラムもヒントとしてお役立てくださいね!