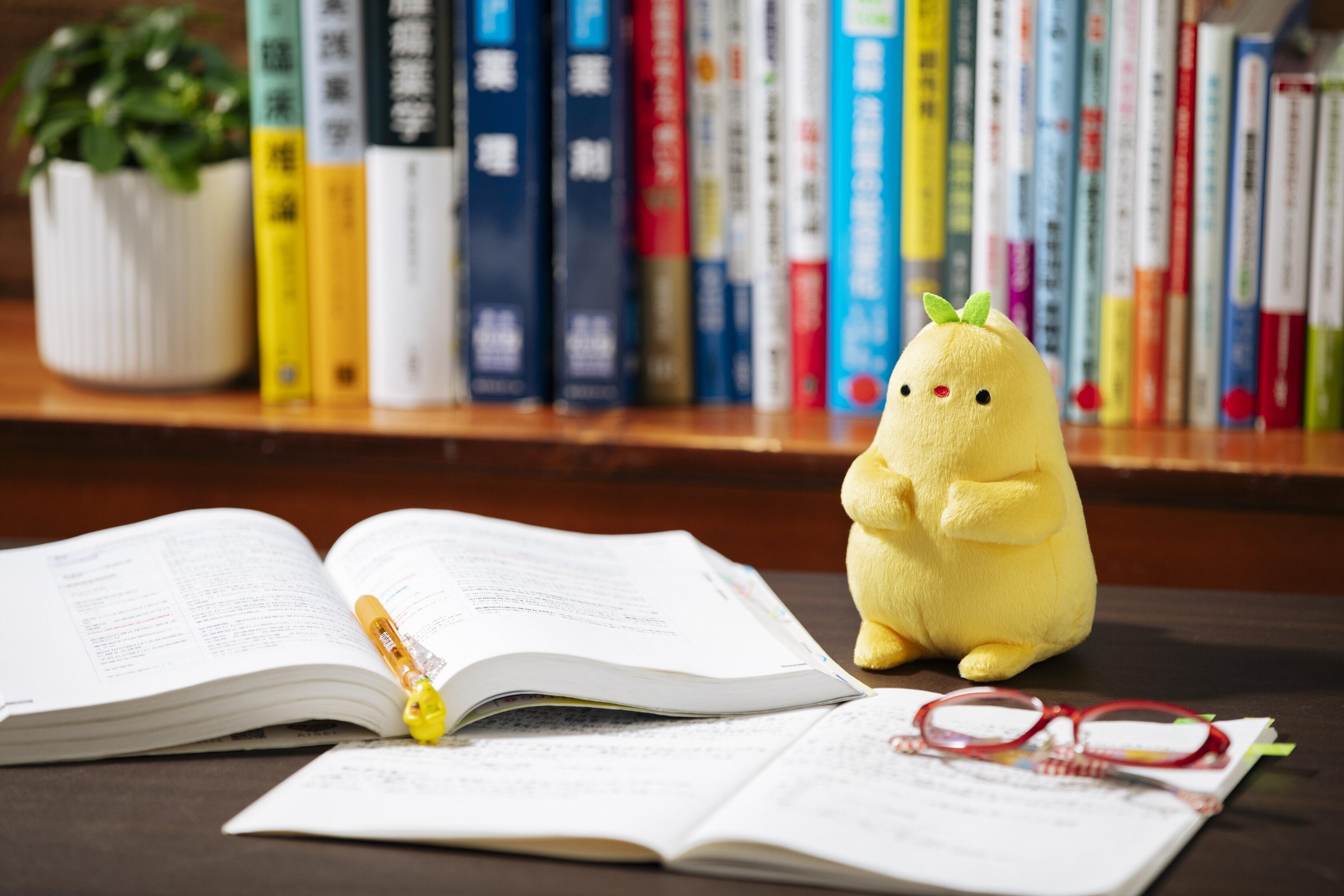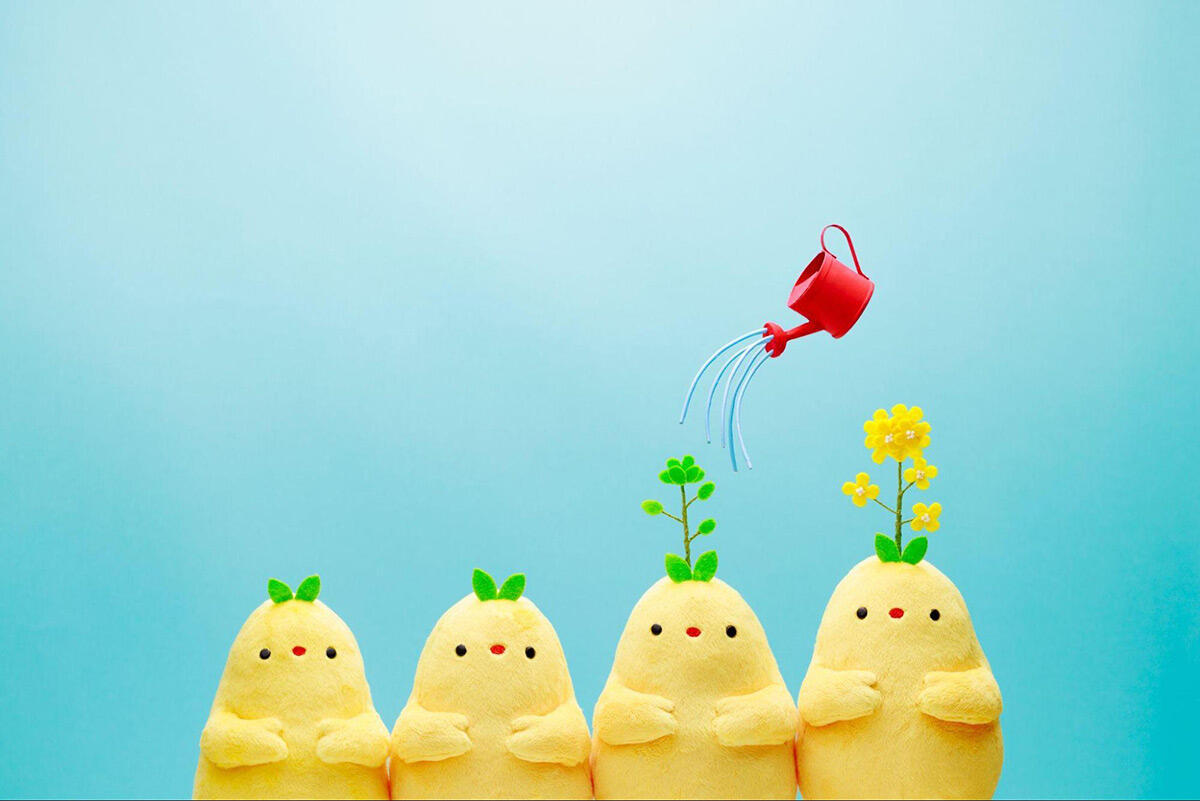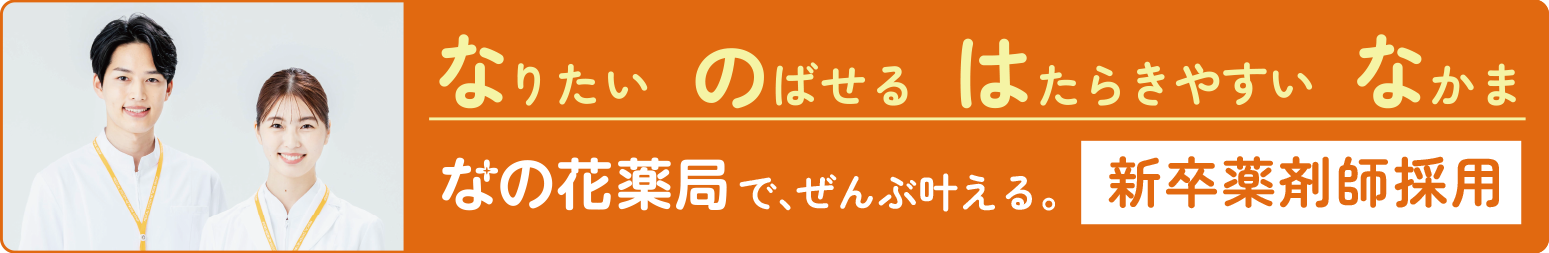2025.06.27
薬剤師の知識
薬学部生必見!実習日誌の書き方をご紹介!効率良く書き進めるコツも
目次
こんにちは!なの花薬局の橋本です。
薬学部の実習期間中、毎日書かなければならない実習日誌に悩んでいませんか?
「何を書けば良いのかわからない」「書くのに時間がかかりすぎる」「書くことがなくて困っている」といった声をよく耳にします。
そこで今回は、実習日誌の基本的な書き方から効率化のコツ、書く内容に困ったときの対処法まで詳しくご紹介します。

薬学部生を悩ませる「実習日誌」。書き方をチェック!
実習日誌は、薬学部生にとって実習期間中の重要な課題の一つです。
しかし、書き方を知らないまま取り組んでしまうと、時間ばかりかかって内容の薄い日誌になってしまいがち。
まずは、実習日誌の基本的な構成と書き方のポイントを確認していきましょう。
実習日誌の基本構成
実習日誌は、一般的に以下の項目にそって記載します。
<日報(毎日記載)>
- 出席状況
- 実施内容(具体的な業務)
- 関わった疾患とその件数
- 学んだこと
- 達成できた点
- 改善すべき点
- 感想・気付き
<週報(週末に記載)>
- 1週間の実習内容のまとめ
- 理解できたこと・理解できなかったこと
- 実践できたこと・実践できなかったこと
- 今後の課題と改善策
作成時に意識すべきポイント
実習日誌を書く際は、感想文ではなく業務報告として作成することを意識してみましょう。
「すごいと思った」「勉強になった」といった抽象的な感想ではなく、具体的にどのような知識やスキルを身につけたのか、どのような課題があるのかを明確に記載しましょう。
また、項目ごとに分けて書くことで、読みやすく整理された日誌になります。
「○○について」「○○の実習」のように、トピックごとに見出しやテーマをつけると、一目で内容がわかりやすくなります。
実習日誌を効率良く書き進めるには?
毎日の実習で疲れて帰宅したあとに時間をかけて日誌を書くのは大変です。
効率良く日誌を書き進めるための具体的なコツをご紹介しますので、ぜひ取り入れてみてください。
テンプレートを作成しておく
毎回一から書き始めるのではなく、あらかじめテンプレートを用意しておくと効率的です。
例えば、日報では以下のような項目を設定しておきましょう。
【実施内容】
- ピッキング( 件)
- 服薬指導( 件)
- 処方解析( 件)
【関わった疾患とその件数】
- (疾患名) 件
- (疾患名) 件
- (疾患名) 件
【学んだこと】
【達成できた点】
【改善すべき点】
【感想・気付き】
テンプレートを使用することで、「今日は何から書こうか」と悩む時間を短縮できます。
また、情報が整理され、後から見返したときに内容を把握しやすくなるのもメリットです。
記入漏れの防止にもなり、同じ項目で比較できるため、変化や進捗を追いやすくなります。
実習日誌を提出される指導者にとっても見やすく、適切なフィードバックや指導を受けやすくなるでしょう。
実習中にメモを取る習慣をつける
実習が終わってから思い出そうとしても、細かい内容は忘れてしまいがちです。
実習中に気付いたことや学んだことを、その都度メモに残す習慣をつけておきましょう。
ただし、メモを取る際には個人情報の流出に十分注意が必要です。
薬局や病院の施設外に情報を持ち出すことになるため、患者さまの個人名の記載は避け、病室番号や年代・性別での記録を心がけてください。
実習中に下書きを完成させる
可能であれば、昼休みや実習の合間に日誌の下書きを作成してしまいましょう。
実習中であれば記憶が鮮明で、短時間で内容の濃い日誌を書くことができます。
実習について詳しく知りたい方は、「薬局実習・病院実習の持ち物や服装は?実習時間や心構えも併せて解説!」もぜひご覧ください。
実習全般の準備について詳しく解説しています。
実習日誌に書くことに困ったら
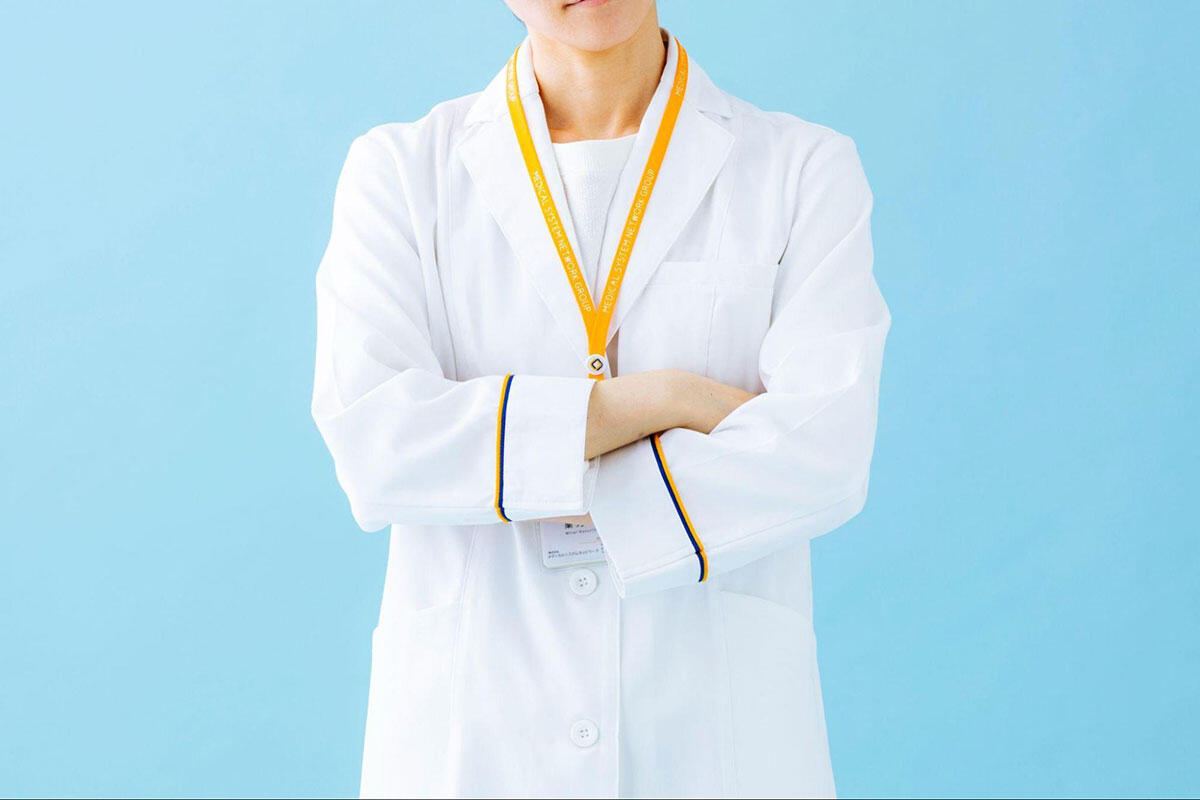
実習が進むにつれて、毎日同じような業務を繰り返すようになり、「書くことがない」と悩む学生は少なくありません。
そんなときに活用できるアイデアをご紹介します。
実習中に扱った薬について掘り下げる
その日に扱った薬剤について詳しく調べ、日誌に記載しましょう。
記載例:【ムコダイン(カルボシステイン)について】
今日の実習でムコダインを扱ったため、詳しく調べ、以下のことを理解した。
- 適応症:慢性呼吸器疾患における去痰、急性気道炎、慢性副鼻腔炎、滲出性中耳炎など
- 特徴:痰を出しやすくする作用に加え、気道粘膜の修復促進作用もある
- 分類:去痰薬(粘液調整・粘液溶解薬)
- 併用注意:咳止め薬(痰の排出を妨げる可能性がある)
- 剤形の工夫:細粒・シロップ・錠剤などがあり、患者に合わせて使い分けが可能
添付文書を活用した日誌の作成は、薬剤知識の習得と国家試験対策に非常に効果的です。
添付文書には、薬効、用法・用量、副作用など、薬剤に関する詳細な情報が網羅されています。
これらの情報を日誌にまとめることで、生きた知識として定着させることができます。
課題の改善策を考える
実習中に起こったミスや課題について、具体的な改善策を考えて記載しましょう。
記載例:【調剤業務での課題と改善策】
今日の実習で以下の課題があった。
- 問題点:薬品の取り間違いをしてしまった
- 原因:薬品名の確認が不十分だった
改善策を検討。
- 薬品を手に取る前に、処方箋を声に出して確認する
- 棚から取り出したあと、再度薬品名を確認する
- 類似薬品については特に注意深く確認する
このように具体的な改善策を考えることで、同じミスの再発防止につながります。
実習中の気付きに触れる
日々の実習で感じた疑問や気付きを記載することも、日誌の内容を充実させつつ学びにつながります。
記載例:【服薬指導での気付き】
患者さまとのコミュニケーションで以下のことを学んだ。
- 気付き:高齢の患者さまへの説明は、わかりやすい言葉を使ってゆっくり行う必要がある
- 工夫:薬の効果を患者さまの生活に関連付けて説明する
- 今後の課題:患者さま一人ひとりに合わせた指導方法を身につけたい
日頃から実習中に積極的に観察し、小さな気付きでも記録していく姿勢が大切です。
実習期間や内容について詳しく知りたい方は、「薬剤師になるための実習期間はどれくらい?内容や場所も詳しく解説!」もぜひご参考ください。
実習日誌の効率的な書き方を知って学びを深めよう
実習日誌は、薬学部生にとって避けて通れない重要な課題。
正しい書き方とコツを身につけることで、効率良く質の高い日誌を作成できるようになります。
テンプレートの活用、実習中のメモなどを実践しながら、日誌作成の時間も短縮していきましょう。
また、扱った薬剤の詳細調査やミスや課題への改善策の検討、気付きの記録などは、薬剤師としてのスキルアップにもつながります。
重要なのは、日誌を単なる課題として捉えるのではなく、自分自身の成長を記録し、将来の薬剤師としての基盤を築く貴重な機会として活用すること。
個人情報の取り扱いには十分注意しながら、積極的に実習に取り組んでくださいね。
なの花薬局では、薬剤師の就活に役立つ情報を随時発信しています。
薬剤師として理想の働き方を目指す方は、ぜひチェックしてみてくださいね!